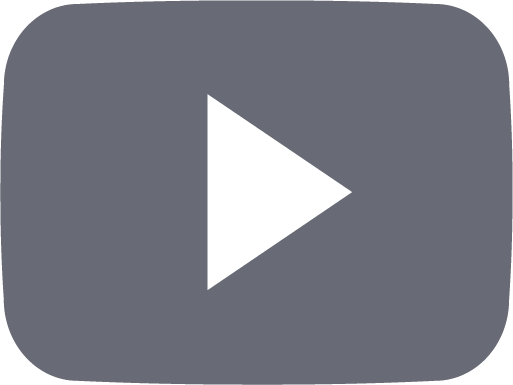無線周波数識別 - モノのインターネットとナノモノのインターネットの新興分野におけるrfidの役割
Fouad Sabry
Translator Kei Imano
Publisher: 10億人の知識があります [Japanese]
Summary
無線周波数識別とは 無線周波数識別は、RFIDとも呼ばれ、電磁界を利用してタグを自動的に識別および追跡する技術です。物に付けられています。無線受信機、無線送信機、および非常に小さな無線トランスポンダが、RFIDシステムのコンポーネントを構成します。 RFIDタグは、近くのRFIDリーダーデバイスからの電磁問い合わせパルスによってアクティブ化されると、デジタルデータ(多くの場合、識別インベントリ番号)をリーダーに送り返します。この番号は、在庫にある商品を追跡するために使用される場合があります。 どのようにメリットがありますか (I)次のトピックに関する洞察と検証: 第1章:RFID 第2章:電子製品コード 第3章:EZ TAG 第4章:マイクロチップインプラント(動物) 第5章:ISO11784およびISO11785 第6章:イヤータグ 第7章:追跡システム 第8章:非接触スマートカード 第9章:クリップされたタグ 第10章:チップのタイミング 第11章:スマートラベル 第12章:ワイヤレスIDの盗難 第13章:Deister Electronics 第14章:ワイヤレスIDおよびセンシングプラットフォーム 第15章:Omni-ID 第16章:リアルタイム位置特定システム 第17章:マイクロチップインプラント(人間) 第18章:Impinj 第19章:チップレスRFID 第20章:学校でのRFID 第21章:動的インテリジェント通貨暗号化 (II)無線周波数識別に関する一般のトップ質問への回答。 (III)多くの分野での無線周波数識別の使用に関する実際の例。 (IV)17無線周波数識別の技術を360度完全に理解するための各業界の266の新しい技術を簡単に説明する付録。 この本の対象者 専門家、学部生および大学院生、愛好家、愛好家、およびあらゆる種類の無線周波数識別のための基本的な知識や情報を超えたい人。