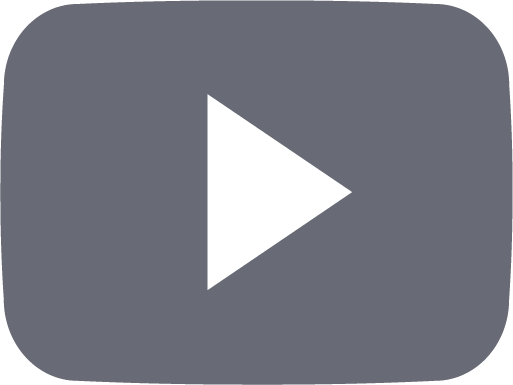自動定理証明 - 基礎と応用
Fouad Sabry
Traduttore Kei Imano
Casa editrice: 10億人の知識があります [Japanese]
Sinossi
自動定理証明とは コンピュータ プログラムを使用して数学の定理を証明するプロセスは、自動定理証明と呼ばれます。 自動推論と数学的論理のこのサブ分野は 1980 年代に開発されました。 コンピューター サイエンスの発展の背後にある重要な原動力は、数学的証明への自動推論の適用でした。 どのようなメリットがあるか (i) 洞察、 および次のトピックに関する検証: 第 1 章: 自動定理証明 第 2 章: カリーとハワードの通信 第 3 章: 論理プログラミング 第 4 章: 証明の複雑さ 第 5 章: メタマス 第 6 章: モデル検査 第 7 章: 形式的検証 第 8 章: プログラム分析 第 9 章: ラマヌジャン マシン 第 10 章: 一般的な問題ソルバー (ii) 自動定理証明に関する一般のよくある質問に答えます。 (iii) 多くの分野で証明される自動化定理の使用例。 (iv) 360 の各業界の 266 の新興テクノロジーを簡潔に説明する 17 の付録 - 度の自動定理証明技術を完全に理解している方。 本書の対象者 専門家、大学生、大学院生、愛好家、趣味愛好家、およびそれらの人々 基本的な知識や情報を超えて、あらゆる種類の自動定理証明を行いたいと考えている人。