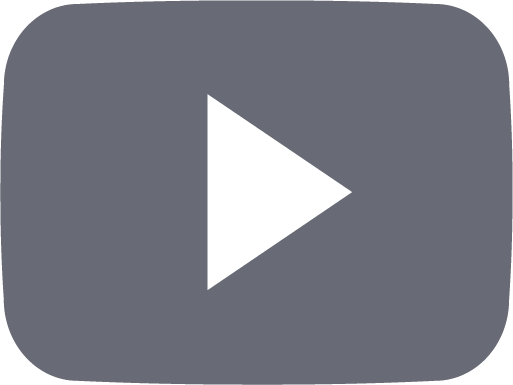人工知能に関する神話 - 基礎と応用
Fouad Sabry
Translator Kei Imano
Publisher: 10億人の知識があります [Japanese]
Summary
人工知能に関する神話とは 人工知能 (ai) の起源は、人工知能に関する神話、物語、噂が広まっていた古代にまで遡ることができます。 熟練した職人によって知性や意識が吹き込まれています。 人間の思考のプロセスを記号の機械的操作として定義しようとした哲学者が、最初に現在の人工知能の種を蒔いた人たちです。 この取り組みは 1940 年代に、抽象的な形式の数学的推論の基本原理に基づいた機械であるプログラム可能なデジタル コンピューターの発明によって頂点に達しました。 研究者のグループは、このガジェットとそれを裏付ける理論の結果として、電子頭脳の開発の見通しを真剣に検討し始めるよう動機付けられました。 どのようなメリットがあるか (i) 次のトピックに関する洞察と検証: 第 1 章: 人工知能の歴史 第 2 章: 人工知能 第 3 章: 中国人の部屋 第 4 章: マービン ミンスキー 第 5 章: 記号人工知能 第 6 章: ニートとだらしない人 第 7 章: 汎用人工知能 第 8 章: 人工知能の哲学 第 9 章: ai の冬 第 10 章: 人工知能の概要 (ii) 人工知能の神話に関する一般のよくある質問に答える。 (iii) 多くの分野での人工知能の神話の使用に関する実際の例。 (iv) 人工知能の神話のテクノロジーを 360 度完全に理解できるように、各業界の 266 の新興テクノロジーを簡潔に説明する 17 の付録。 この本の対象者 専門家、大学生、大学院生、愛好家、趣味人、そしてあらゆる種類の人工知能に関する神話についての基本的な知識や情報を超えたいと考えている人。